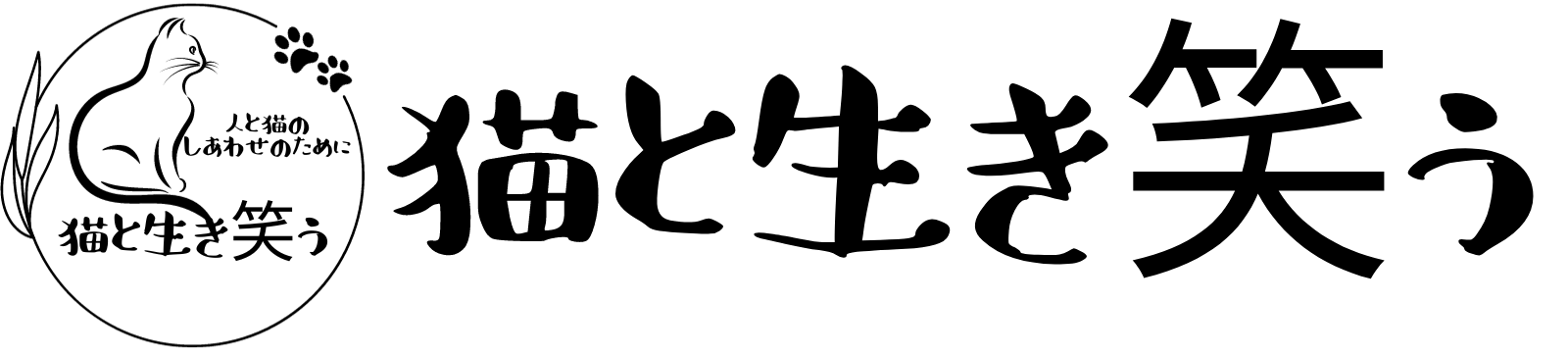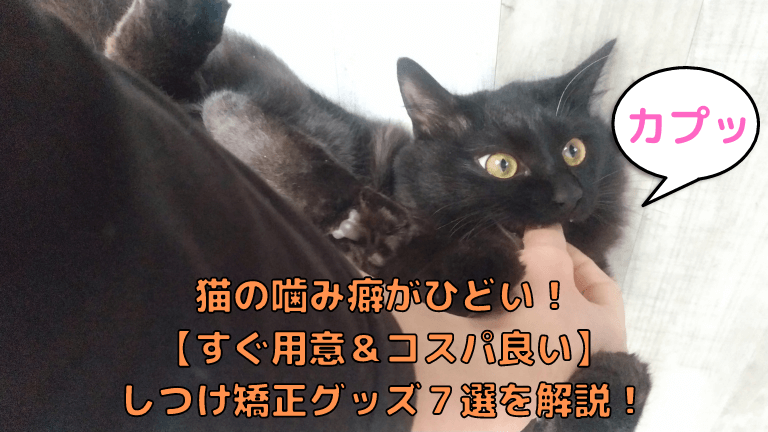【結論】
ぬいぐるみやおもちゃを代わりに噛ませる。ミニ霧吹きや超音波で噛まれたら嫌な目に遭うと覚えさせることが効果的。他にも爪切りでキック対策をする、スポーツインナーで肌を防御することもおすすめです。
猫の噛み癖は、多くの飼い主が直面する悩みです。はじめは可愛らしかった噛みつきも、続くと笑えなくなっていきます。人の手足から電源コードなどの危険な物まで、ありとあらゆる物を噛もうとするため非常に危険な行為です。
早い内から噛み癖を矯正しないと、甘噛みから「本気噛み」へと発展し力強く噛むようになります。
この記事では、猫の噛み癖と付き合い続けて20年以上の筆者「たけのこ」が猫の噛み癖対策グッズを解説します。
 たけのこ
たけのこ猫に噛まれない飼い主さんを目指しましょう!


猫ブロガー
たけのこ(Takenoko)
プロフィール
(タップで詳細を表示)
猫と暮らして20年以上。猫ニュースメディアのライターとして活動。いままで500本以上の猫に関する記事を執筆!猫たちの幸せに繋がればという想いで当サイトを運営しています。ペットフード/ペットマナー検定合格。飼い猫を主役とした絵本も出版。


猫YouTuber・ライバー
黒猫トモくん(Tomo)
プロフィール詳細
(タップで詳細を表示)
運営者の飼い猫であり当サイトの編集長。保護猫出身。黒猫。甘えん坊な男の子。猫専門配信アプリnekochan公式ライバー。YouTubeも配信中!
猫の噛み癖4つの理由


そもそも猫たちはどうして大好きな飼い主さんを噛んでしまうのか?その理由を知ることが噛み癖を克服する第一歩です。



まずはその理由を解説します!
①飼い主を「おもちゃ」だと思っている


自分の手足をおもちゃ代わりにされている飼い主さんもいらっしゃるのではないでしょうか?実はこの行為は猫に噛み癖を付けさせる原因の一つとなります。
手足で遊ぶ習慣があると、猫は「飼い主さんはおもちゃ」と覚えてしまいます。結果として、飼い主さんを噛むことが当たり前となり、日常的な噛み癖に繋がってしまいます。
②子猫の甘噛み


噛み癖の多くは子猫の甘噛みに由来します。子猫は「甘えたい」、「歯の生え変わりでムズムズしている」などの理由で、飼い主さんに甘噛みしてしまいます。


③噛むと言うこと聞いてくれるから


猫に噛まれてから遊ぶ、なでる、ご飯を用意するなどを習慣的にしてませんか?噛まれてから猫の要望を叶え続けると、「噛んだら飼い主さんが言うこと聞いてくれる」と猫が勘違いしてしまいます。
④愛撫誘発性攻撃行動


撫でているときに噛まれることを「愛撫誘発攻撃行動」といいます。
これは「さわるな!」という猫なりの意思表示です。基本的に猫は触られることを嫌がりやすいので、嫌がられたら撫でるのを止めましょう。あまりにも「しつこい」と猫のストレスとなり嫌われる原因となります。
一方で特定の個所を触られるのをやたらと嫌がる場合は、実はケガや具合が悪い可能性もあります。
猫の噛み癖対策グッズ7選


猫の噛み癖をしつけることは、簡単ではありません。解決には、数か月単位の長期戦を覚悟する必要があります。ここからは、そんな長期戦をサポートするオススメグッズを紹介します。



すぐ用意できて、コスパもバッチリ!
①ぬいぐるみ


猫に噛まれる!そんなときに役立つのが「ぬいぐるみ」です。商品によっては「けりぐるみ」ともいいます。


使い方はシンプル。噛まれたら近くにある「ぬいぐるみ」を差し出すだけです。ターゲットが「ぬいぐるみ」に移って代わりにガブッと噛まれ、甘噛みキックされてくれます。


継続していく内に「飼い主ではなく、ぬいぐるみを噛む」と覚えて、飼い主さんに甘噛みすることも減っていきます。最初はぬいぐるみが可哀想に思えますが、明日は我が身。ぬいぐるみには、尊い犠牲になってもらいましょう。
②爪切り


猫の噛み癖に爪切りは関係ないよね?と思われるかもしれませんが、実はそうとも言い切れません。というのも、猫は甘噛みをする際、後ろ脚で「猫キック」を行います。俗にいう「猫の甘噛みキック」という仕草で獲物にトドメを刺す行動です。


この「猫の甘噛みキック」見ている分には可愛いですが、けっこう強力。興奮して後ろ足の爪が出てくるため、ケガすることもあります。「猫の甘噛みキック」で怪我しないためにも、猫の爪切りは必須アイテムです。
ちなみに猫の爪切りは人間用の爪切りで行ってもOKです。ただ、猫爪切り初心者の方は慣れるまで苦戦します。「爪切りに慣れていない」という方は猫用爪切りの方がスムーズです。


③超音波アプリ
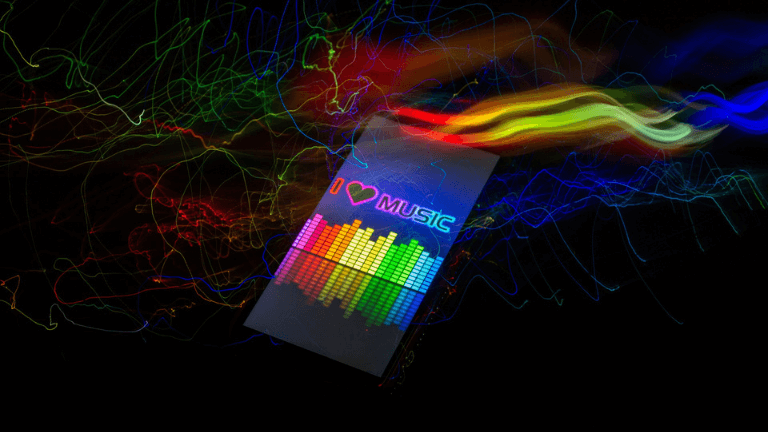
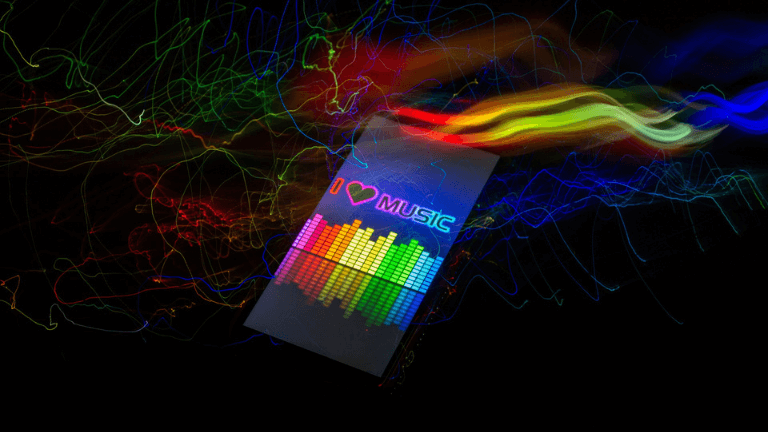
猫のしつけ方法として「音」を利用する方法もあります。オススメなのは「超音波バリア」。手軽で簡単に使用でき、YouTuberの「ヒカキン」さんも試したことがあります。猫が嫌がる音域が最初から設定されており、スムーズに使えて便利です。
ただし、筆者「たけのこ」が試した際、効果の幅には個体差があると感じた点と継続して使い続けると猫が慣れてしまう点が微妙でした。最初は警戒し離してくれましたが、使い続けると慣れてしまったのか効果がありませんでした。


④電源コードカバー


猫の噛み癖は飼い主だけでなく、周囲の物が対象となることも多いです。力強く噛んで物を壊してしまうこともあります。家庭内で危険度が高いものは「電源コード」。ヘタしたら感電してしまいます!
おもちゃと認識されやすいため狙われることが多く、筆者「たけのこ」も飼い猫トモくんから隠し続けていました。とはいえ、すべて隠すのは限界があり生活の利便性も損なわれてストレスとなります。


そこで役立つのが「電源コードカバー」。装着することでコードを噛まれても、感電事故が起こる可能性を小さくできます。色んなタイプが販売されており設置自体も簡単!イチイチ猫がコードを噛む度、叱らずに済むのも嬉しいところです。
コードカバーは100均で販売されているのでも十分役立ちますが、噛まれ続けるとボロくなってきます。


⑤霧吹きスプレー


猫のしつけ方として霧吹きは、有名な方法のひとつ。甘噛みをはじめ猫がイタズラ行動したとき、水に濡らすことで「この行動したら嫌な目に遭う」と覚えさせる方法です。
しかし、通常の霧吹きは大きく携帯できないため使いたいときに手元にないことが大半。また、多くの情報サイトでは「猫にバレると嫌われるので、霧吹きを見られてはいけない」という内容が書かれています。



いや!無理!


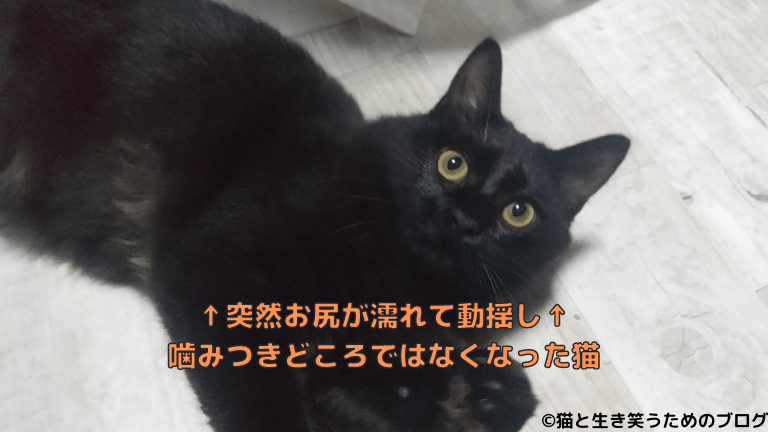
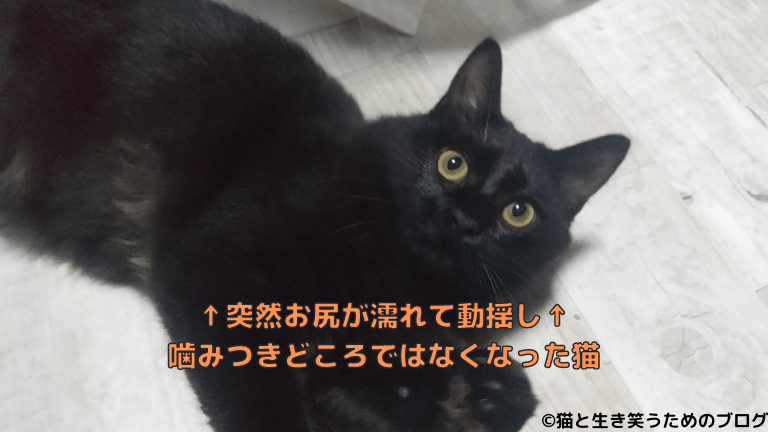
そこで筆者「たけのこ」がアレンジした方法が、ミニ霧吹きスプレー。
本来は香水などを持ち運ぶ用途の物です。裾やポケットに隠せる大きさで携帯しやすいので噛まれたとき、すぐ使えて、バレる前に隠せます。筆者「たけのこ」は100均で販売されている物を使っていますが、それなり満足しています。
ただ、100均の物は使っていて、「押しているのに水が出ない」など品質・耐久性が微妙に感じることはあります。不具合をストレスに感じやすい方は、少しだけ価格が上の商品を利用することをオススメします。



中身は水道水でOKです
⑥歯磨きおもちゃ


噛み癖対策として猫用ハミガキおもちゃで、こまめに遊び狩猟本能を満たしてあげることも効果的。遊びついでに歯のケアもできます。猫にとっても歯磨きは重要ですが、嫌がる子も少なくありません。
理想はハブラシでごしごしですが、難しい方はハミガキおもちゃを導入するのも一つの選択肢となります。もしくは、下記の記事で紹介しているようなフードを取り入れてあげることもおすすめです。




猫と遊ぶ時間は1回5分程度の短時間で十分。瞬発的な狩りをしていた猫にとっては長時間より短時間の遊びの方が相性いいです。短時間の遊びを複数回こまめに取り入れてあげると、猫の運動不足を解消しストレスによる噛みつきも少なくなります。




⑦スポーツインナー&靴下


猫の噛み癖しつけ方法は、基本的に噛まれた後に行うものばかり。結局「痛い」思いをすることには変わりありません。そこで様々な試行錯誤を繰り返した筆者「たけのこ」は、室内でもスポーツインナーと靴下を装着することで防御力を高めています。
素肌を直接噛まれるよりも痛みは格段に小さくなります。「当たり前だよね」と思われた方こそ、是非試していただきたい。素肌を噛まれるより大分マシです。


特に甘噛みは、一応猫も手加減しているため「インナー&靴下」を着ているとケガや噛み跡が残りにくいです。
- 夏は換気の優れたスポーツインナーがおすすめ
- 冬は暖かいヒートテックもアリ
- 靴下はできるだけ、ハイソックスなど長めな物を推奨



痛いのが嫌な人は是非試してみてください
猫の噛み癖をやめさせるしつけ方法とは?
噛み癖を直すためには、猫の気持ちを理解しながら、一貫性のある対応を続けることが大切です。ここでは、日常生活で実践しやすいしつけ方法をご紹介します。
噛まれても過剰に反応しない
猫に噛まれたとき、大声を出したり、強く手を引いたりするのはNGです。猫は「反応があった=楽しい」と学習してしまい、噛む行動を強化してしまうこともあります。冷静に手を引き、「噛むと遊びは終わる」というルールを伝えましょう。
「ダメ」と伝えるときのタイミング
噛んだその瞬間に「ダメ」と短く低い声で伝えることで、猫は「これをすると嫌がられる」と学びやすくなります。ただし、時間が経ってから叱っても効果は薄く、むしろ混乱させてしまうので注意が必要です。
手を使って遊ばない習慣をつける
手で直接猫とじゃれ合って遊ぶのは、噛み癖を助長する原因になります。おもちゃを介して遊ぶ習慣をつけることで、「噛む対象は人ではない」と自然に学ばせることができます。
しつけは一貫性が大事
家族の中で対応にバラつきがあると、猫は混乱して学習できません。家族全員が同じルール・対応を守ることが、しつけ成功の鍵です。
噛み癖がひどいときは病気の可能性も?
通常の噛み癖であれば、しつけや環境改善で徐々におさまることが多いですが、急に噛むようになった・異常に攻撃的になったといった場合は、病気やストレスのサインかもしれません。
突然噛むようになったら要注意
これまで穏やかだった猫が、ある日突然噛みつくようになったという場合、体に不調を抱えている可能性があります。痛みや不快感があると、触られるのを嫌がり、防御的に噛むことがあります。
ストレスや体調不良のサインかも
環境の変化(引っ越し・来客・他のペットの導入など)は、猫にとって大きなストレスになります。トイレや食欲の変化、嘔吐や下痢など、他の体調面にも変化が見られたら注意が必要です。
受診の目安と動物病院でできること
「元気がない」「いつもと違う場所で寝ている」「急に人を避けるようになった」などの変化が見られる場合は、早めに動物病院へ相談しましょう。身体の異常がないか、専門の目で確認してもらうことで安心できます。
成猫の噛み癖は治る?子猫との違いとは
子猫のうちの甘噛みはよくあることですが、成猫でも噛み癖が残ってしまうことは珍しくありません。ただし、年齢によって対応方法に少し違いがあります。
子猫は遊びの一環で噛んでしまうことが多く、学習によって比較的矯正しやすいです。対して成猫は、過去の経験やストレスが噛み癖に影響している場合もあるため、焦らずじっくりと対応する必要があります。
猫の噛み癖 まとめ


猫のしつけは他の動物に比べて難しく時間がかかります。だからといって何も対策しなければ、次第に本気噛みへと発展していく恐れがあります。
猫の本気噛みは痛いどころの騒ぎではなく、牙が肉を貫くこともあり得ます。今回解説したグッズを活用して、猫の噛み癖ライフから脱出してください。